ホタルゲノム解読しました
- Manabu
- 2019年3月5日
- 読了時間: 3分
報告が遅れましたが、ホタルゲノムの論文がeLifeに出ました!(去年の11月に)
そして、その和文解説を実験医学のカレントトピックスというコーナーに乗せていただきました。
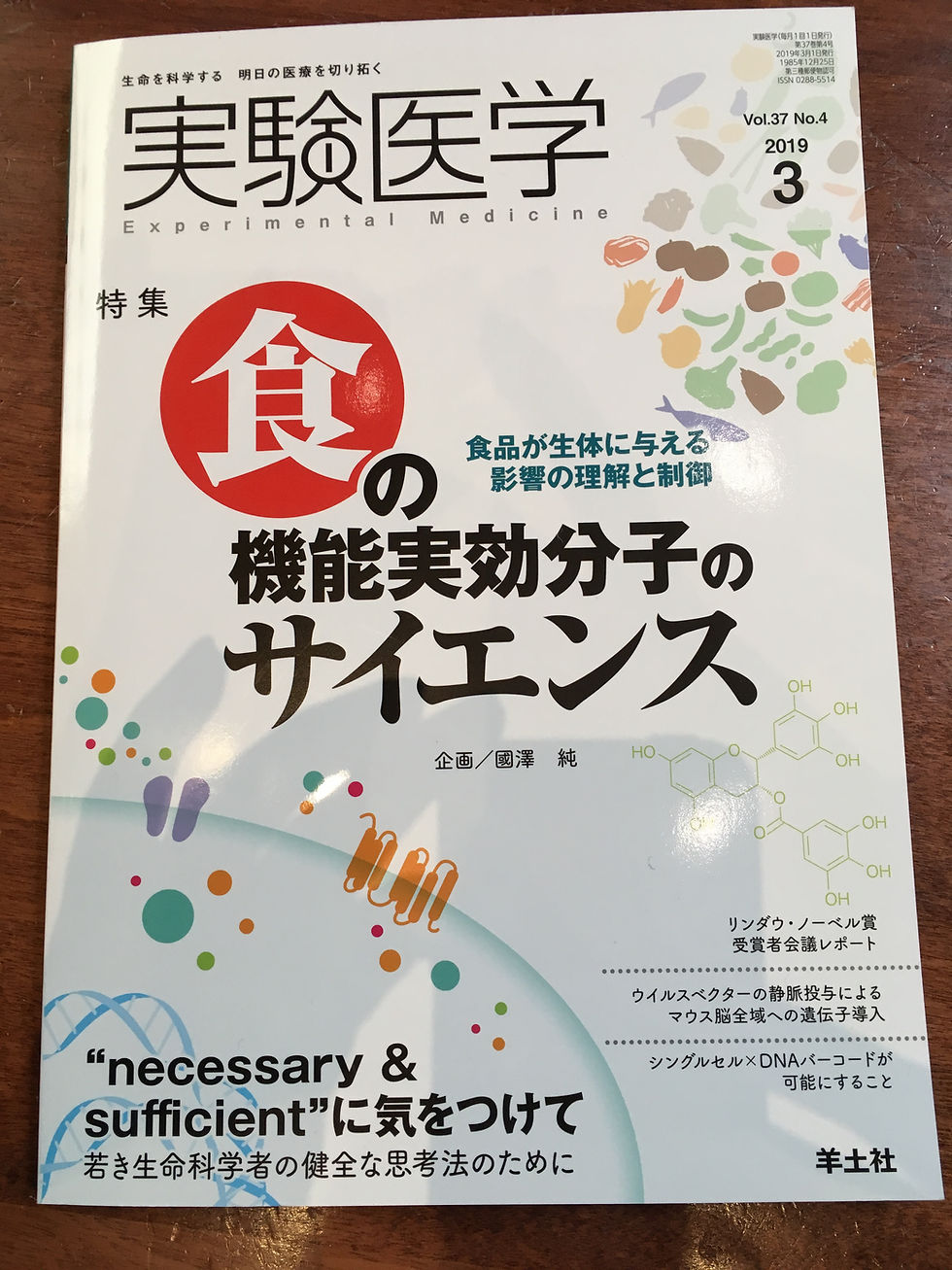

英語の原著論文はサプリメンタルを含めると100ページを超える超大作。基礎生物学研究所のプレスリリースではその中のメイントピックである「ホタルにおけるルシフェラーゼ遺伝子の進化」について詳しく書いてあります。
実験医学に掲載された解説では、もう一つの光る甲虫であるヒカリコメツキを含めた遺伝子解析から、甲虫ルシフェラーゼの平行進化について書いています。また、発光器で特異的な発現を示す遺伝子群を特定し、さらに、発光の進化の原動力となった毒(ルシブファジン)を生合成する遺伝子にも言及しています。(そして、なんとヘイケボタルにはそのルシブファジンが無いことがわかりました)。
また、研究成果の総括を1月に基礎生物研究所で行われたホタルゲノムシンポジウムで発表してきました。
プレスリリースの解説文と実験医学の内容で、元の論文の美味しいところは9割を網羅できていると思います。機会があればぜひお読みください。
そして残りの1割をここのブログで書こうと思います。
サブタイトルは、
ヘイケボタルは自分の光をお尻の目で見ている?
ヘイケボタルのゲノムを解読し、どのような遺伝子を持っているかを明らかにした我々は、続いて、発光器に特異的に発現している(働いている)遺伝子を調べた。
そこで、ヘイケボタルの発光器のトランスクリプトームで光を受容するタンパク質オプシンが見つかった。昆虫が目で光を感知するのに使っているオプシンには紫外領域を感知するUVオプシンと(ヒトにとっての)可視光域を感知する長波長(LW)オプシンがある。UVオプシンとLWオプシンはヘイケボタルの頭部において高発現を示した。さらに、あまり機能がわかっていないRh7オプシンが見つかってきた。そして面白いことに、Rh7オプシンは発光器だけで発現していた。一方で、UV,LWオプシンは発光器での発現は見られない。このことは、ヘイケボタルは発光器で発現しているRh7オプシンにより、自身の発光を感知しているのではないかという妄想を掻き立てる。(機能証明はまだまだこれから)。
チョウチョは実はお尻に光受容体を持つことが知られており、これは交尾した際に相手の体が覆いかぶさることでできる影を認識し、文字通りの「交尾」をモニターしているらしい。(Arikawa and Aoki, 1982)。また、他の発光生物においては、クシクラゲMnemopsis leidyi の発光細胞には発光タンパク質とともに3つのc-opsinが発現しているらしい。ハワイのミミイカbobtail squid Euprymna scoloesでも共生発光器官にc-opsinの発現が確認されている。発光生物においては、発光器でのオプシンの発現というのは共通の必要な条件なのかもしれない。
とか思いつつ、北米のマドボタル科のPhotinus pyralisを調べてみると、Rh7オプシンはあるものの、発光器での発現は見られなかった。(1)そもそもRh7オプシンは発光の感知に関与していないかもしれないし、(2)ヘイケボタルのグループでのみRh7オプシンが機能しており、(3)Photinusでは別の仕組み(オプシン)があるか(4)そもそも見ていないのかもしれない。

図 オプシン遺伝子の系統樹(A)と発現量解析(B)
ヘイケボタルのUVオプシン、LWオプシンcオプシン、Rh7オプシンの遺伝子発現量を比較した(n=3)。Photinus の遺伝子は灰色(n=1)。Rh7オプシンは発光器(Lantern)でのみ高く発現しているが、その他のオプシンは頭部以外では発現していない。(Fallon et al., 2018, eLife)より改変。赤で囲ったのがヘイケボタルのRh7オプシン。緑で囲ったのが、クシクラゲとミミイカのオプシン。




コメント